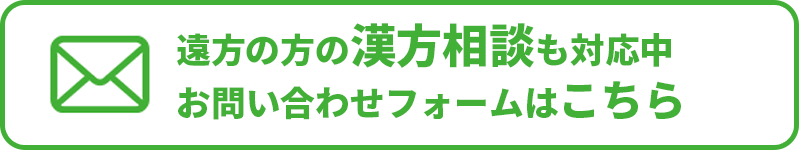今後何回かに分けて養生法について書いてみたいと思います。
先ずは養生法とは何かを書いて、その次に養生法の種類(分類)について書いていきます。そして、分類した個々の養生法について書いていこうと思います。
養生法の定義に関してはそれほど大きな違いは無いですが、養生法の分類の仕方は漢方(中医学)の流派や個々の先生方の考え方によって異なる場合がありますし、養生法の内容も四季の養生法などは大きくは変わらないと思いますが、それ以外の養生法は先ほどと同様漢方(中医学)の流派や個々の先生方の考え方によって異なる場合があります。
そのため、私が書くことが絶対だという事ではないです。
漢方薬局ハーブスはこういう理論に基づいて治療を行っているということを理解していただければ良いと思っています。
そして、私が書こうと思っているのは、日ごろ私が自分の漢方薬局で患者さんにお話しする内容に近いことです。
ただ、漢方は個々の患者さんの体質を重視するので、患者さん一人ひとりその状況に応じてお伝えする養生法は異なりますし、毎回、漢方相談の度に、養生法についてお話しするわけでもありません。
漢方相談をする中で必要を感じた時にお話しするようにしています。
私は沢山の養生法をお伝えする(患者さんの知識をどんどん増やしていく)ことよりも、1つの事(本当に患者さんにとって必要な事)を患者さんがご自身で実践し続けることが大事だと思っています。
知識が増えるだけでは身体は変わらないのです(良くならないのです)。(知っているけど数回しかやっていないとかでは身体は変わらないのです)

どんなに身体に良い事でも継続しないと身体は変わらないです。
例えば、筋トレの方法何十通りも知っているのに、筋トレしなかったら筋肉つかないですよね。みたいな話です。
こういった前提があるので、皆さんが知らないような珍しい養生法を次々とお話しするようなことはしません。
どちらかといえば、それ知ってるとか、聞いたことあるような養生法の話になると思います。
ただし、実践すれば誰がやっても安全で、確実に効果のあることをお伝えしたいと思っています。
ではまず最初に養生法の定義(養生法とは)についてお話します。
養生法(養生法)とは
心身の健康を保ち、病気を予防し、長寿を全うするための生活習慣や考え方の総称です。
もっと簡単に言えば『健康に過ごすために日ごろ行うこと』くらいの感じの理解で良いと思います。
この考え方は西洋医学の予防医学の考えに近いと思いますが全く一緒という訳ではないです。
そこでこれも一般論となってしまいますが西洋の予防医学と養生法について書いてい見たいと思います。
| 西洋医学の予防医学 | 東洋医学の養生法 | |
| 基礎となっているもの | 西洋医学の医学理論に基づく(解剖学や生理学など) | 東洋医学の理論に基づく (陰陽五行、五臓六腑、気血水など) |
| 方法 | ワクチン、定期健診およびそれに基づく食事や運動指導など | 食養生、気功(呼吸法)、時節養生(四季の養生法)など |
| 目的 | 病気の発症を防ぐこと | 健康に寿命を全うする |
| 健康観 | 病気が無い状態 | 心身の調和・自然との調和がある状態 |
| 視点 | 主に他覚的視点を重視 検査値など数値化できるもの画像データなど目に見えるもの (風邪で39℃の高熱が出ているなら高熱を重視) |
主に自覚的視点を重視 数値化できない本人の自覚症状(何となくだるいとか体温は39℃と風邪で高熱が出ていても寒気の方を重視) |
西洋の予防医学は検査値などの他覚的所見を基準として、その基準を満たさない項目に対しての予防という視点でアプローチしていきますが、東洋医学の場合は数値化できない本人の不調(病院の検査では何も引っかからないが、何となくだるいなどの)自覚的なものを重視してその視点からアプローチしていゆく点が大きく異なっていると思います。
次回以降は最初に書きましたように養生法の分類や個々の養生法について書いていこうと思います。
もし、東洋医学や漢方、それに付随するような内容に興味のある方はおすすめ記事を読んでみてください。
また、比較的めずらしい症例や東洋医学のうんちくなどに興味のある方は公式Instagramもご覧ください