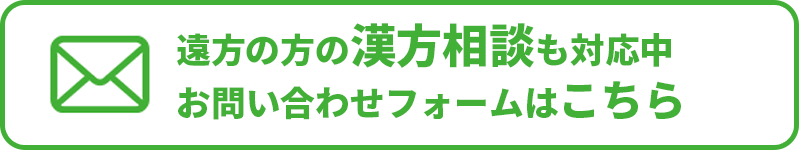このページは広島にある起立性調節障害の情報ページです。
ここでは起立性調節障害の概要、症例、症状、原因(西洋医学)、原因(東洋医学)、漢方的な治療、関連する疾患・症状などについて書いていきます。
起立性調節障害とは
思春期前後の年齢の方に多くみられる疾患で、自律神経の調節がうくいかない結果『めまい』『立ちくらみ』、『動悸』などはじめとしたさまざまな症状を呈することが多い疾患です。
起立性調節障害は学童期~思春期に多い疾患ですから、結果として遅刻や欠席することが多くなり、それがひどくなると不登校の原因にもなります。そのため、しっかりと治療することが大事な疾患です。
起立性調節障害は症状によって以下の4つのタイプ区別されるのですが、実際にはきっちりと4つのどれかに分類されるよりも複合していることの方が多いように思います。
起立直後性低血圧・・・ほぼ起立性低血圧のこと
遅延性起立性低血圧・・・立っていると徐々に血圧が低下するもの
体位性頻脈症候群・・・姿勢などを変えた時、血圧は下がらないが頻脈になるもの
神経調節性失神・・・立っていると急激に血圧が低下し倒れる(失神する)もの
起立性調節障害の症例

起立性調節障害の症状
・『立ちくらみ』、『めまい』の症状がある
・朝なかなか起きられない、午前中調子が悪い
・立っていると気分が悪くなる、それが悪化すると倒れる(失神する)
・少し動くと動悸や息切れがする
・日ごろから疲労感、倦怠感がある
・顔色が悪い(青白い)
・入浴時に気持ち悪くなったり、頭痛がしたりする
・乗り物酔いを起こしやすい
・食欲不振
・腹痛
・ストレスを感じると気分が悪くなる
等など多岐にわたります。
起立性調節障害の原因(西洋医学)
起立性調節障害の主な原因は自律神経の調節機能がうまくいっていないからと考えられています。
ではどうして自律神経の調節機能がうまくいかないのか?というと、起立性調節障害を発症しやすい学童期~思春期の頃というのはまだ身体の機能が発達途中なのです。
そのため人によって自律神経の機能の発達にばらつきがあり、まだ十分に発達していない人が発症しやすいということなのだと思います。
そのため、外的な要因(刺激)に影響を受けやすくもあるのです。
起立性調節障害に影響を与える要因
季節、気候(天候)、健康状態(この症状以外の)、肉体的ストレス、精神的ストレス、生活リズム、運動量(身体の筋肉量)、食事量、BMIや体脂肪率(起立性調節障害の方は痩せている人が多いです)
起立性調節障害の原因(東洋医学)
気滞(きたい)
気滞とは東洋医学的な気の巡りが悪くなっている状態のことを指します。これが西洋医学の自律神経失調に近い意味合いで用いられます。
水毒(すいどく)
水毒とは身体の中の水の偏在(へんざい→かたより)を表す言葉です。東洋医学では水が不足しても過剰になっても病気の原因になると考えています。起立性調節障害は東洋医学的には水が過剰な状態になっていると考えます。
気の上衝
気が上に上がった状態です。今の言葉で近いものはテンパるとかものすごく焦るとかかな?と思います。
起立性調節障害の治療(東洋医学)
起立性調節障害は東洋医学では上記で挙げたような気滞、水毒、気の上衝が原因となっています。
ただし、起立性調節障害はこの3つのどれかで起こるというよりもこれらの3つの原因が複合して起こっていることがほとんどです。そのため、この3つの漢方薬を組み合わせて用いることになります。そしてそれぞれ複数の漢方薬が存在します。
その漢方薬の組み合わせは患者さんの体質も症状も異なるため、漢方薬の組み合わせは患者さんによって異なりますし、漢方治療を行ってゆくと患者さんの症状も変化しながら軽減していきます。その変化に合わせて漢方薬の組み合わせも変化していきます。そのため、それに応じて相談を行っていきます。
起立性調節障害と関連するページ